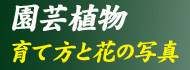|
|
|||||||||||||||||||
ヒュウガミズキ |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【ヒュウガミズキについて】 |
|||||||||||||||||||
|
ヒュウガミズキ(日向水木)は、近畿地方北部から岐阜県、富山県などに分布しているマンサク科トサミズキ属の落葉低木で、トサミズキの近縁種です。ヒュウガミズキという名前が付いていますが、宮崎県の日向地方には自生していないことから、地名が名前の由来ではないようです。 それはさておき、トサミズキと比較すると、樹形はずっと小ぶりで枝打ちがさらに細かく、花も密につきます。撮影時期からすると開花時期は、トミミズキよりは少し遅いように思われます。 【栽培メモ】 午前中だけ日の当たるところに植え付けていましたが、写真のように、よく花が咲いていました。丈夫で育てやすく、また、それほどスペースを取りませんので扱いやすい花木と言えます。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【ヒュウガミズキの概要】 |
|||||||||||||||||||

樹高 樹高は1~1.5mほどで株立ち状となります。トサミズキと比較すると小型で、枝が密に出ます。 花 花は淡黄色で、長さは1.5㎝ほどです。ひとつの穂につく花数は2~3と少ないですが、枝打ちが細かいことから、花も密に咲きます。 耐寒性・耐暑性
耐寒性、耐暑性があります。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 やさしい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Corylopsis paucifiora 学名の説明 Corylopsis・・・・・ Corylus(ハシバミ属)+ opsis(・・・に似た)が語源です。 paucifiora・・・・・「少数花の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
近縁種にトサミズキやニオイトサミズキがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 -私はこう育てる- |
|||||||||||||||||||
|
栽培のポイント ※ 徒長枝には花芽がつきにくいので、1~2月ごろに長く伸びた枝を花芽の上で切り取ります。 植え付け 秋は11下旬~12月中旬頃、また春は2月下旬~3月中旬頃が適期です。 深さ30cmほどの植え穴を掘り、掘り上げた土の3割程度の腐葉土若しくはバーク堆肥を入れ、庭土とよく混ぜ合わせて植えつけます。植え付け後は、たっぷりと水やりをして風で苗木がぐらつかないように支柱を立てておきます。 コンパクトな樹形になりますので鉢植えでも育てられます。 
鉢植えの用土 赤玉土、鹿沼土、腐葉土(又はバーク堆肥)を4:3:3程度に混ぜたものなどを使います。 植え場所・置き場所 庭植えの場合は、土質は選びませんが、日当たりのよい場所に植えると花付きがよくなります。半日陰程度でも問題はありません。 鉢植えも日当たりのよいところに置きますが、夏場は乾燥しすぎないよう半日陰に置くと、水やりの手間が多少省けます。 植え替え 鉢植えの場合は、鉢が小さいときは毎年、大きい鉢に植えているときは2年に1回を目安に植え替えをします。 鉢から抜いて、表土と根鉢の三分の一ほど土を落として、一回り大きい鉢に植え替えます。同じ大きさの鉢を使うときは、少し多めに古い土を落として植え替えます。 剪定 樹形は自然に整いますので、剪定はあまり必要ではありません。 花芽は、その年に伸びた新枝の葉腋につきますが、徒長枝には花芽がつきにくいので、1~2月ごろに長く伸びた枝を花芽の上で切り取ります。 肥料 庭植えの場合は、冬に寒肥として油カスに骨粉を少し混ぜたものを木の周りに施します。 鉢植えは、冬場と花後に緩効性の固形肥料を与えます。 病気・害虫 特にありません。 |
|||||||||||||||||||