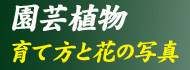|
| |||||||||||||||||||
ツメレンゲ |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【ツメレンゲについて】 |
|||||||||||||||||||
|
ツメレンゲ(爪蓮華)は、関東地方以西、四国、九州、そして朝鮮半島などに分布しているベンケイソウ科イワレンゲ属の多肉質の多年草です。 ツメレンゲの名前の由来は、イワレンゲ(O. malacophylla)に似ていて、細くとがった葉がけものの爪に似ているからと言われています。また、イワレンゲのレンゲというのは、多数の葉が重なり合った姿をレンゲ、即ちハスの花にたとえたものと言われています。 【栽培メモ】 ツメレンゲは多肉質の多年草ですが、比較的寒さ、暑さに強く過湿にならないよう注意すれば育てやすいと言えます。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【ツメレンゲの概要】 |
|||||||||||||||||||

草丈 10~20㎝ほどで、栄養繁殖して株立ちになります。春から秋は緑色の葉をしていますが、秋になるとだんだんと色づいてきます。 花 花茎は10~30㎝ほどに伸びて、小さな花が集まって穂状に咲きます。花を付けた株は枯れてしまいます。 耐寒性・耐暑性
比較的耐暑性があり、耐寒性もあって温暖地では戸外で冬を越します。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 ※ 比較的やさしい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Orostachys japonica 学名の説明 Orostachys・・・・・ギリシャ語の(山)+(穂)が語源です。 japonica・・・・・「日本の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
この仲間には、イワレンゲ(O. malacophylla)やコモチレンゲ(O. malacophylla var. boehmeri)などがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 -私はこう育てる- |
|||||||||||||||||||
|
栽培のポイント ※ 過湿にならないようにします。 植え付け 3~4月が植え付けの適期ですが、ポット苗であれば秋でも差し支えありません。園芸店やホームセンターで見かけることがあまりないように思いますが、ネットなどでも販売されています。 ロックガーデンなどであれば庭植えもできますが、通常は鉢植えで育てます。 鉢植えの用土 多肉植物用の用土など水はけのよいものを使います。 
置き場所 春と秋は日当たりのよいところに置いて育てます。長雨の続きそうなときは、雨のかからないところに移した方が安全です。 植え替え 1~2年経つと根詰まり気味になってきますので、株分けを兼ねて春に植え替えるようにします。 日常の管理 多肉質の多年草ですので、過湿にならないよう、やや乾燥気味に育てます。 開花時期には、花茎が曲がらないように鉢の向きを定期的に変えるようにします。 夏の管理 耐暑性はありますが、夏の強い日差しを嫌いますので、鉢やプランターは半日陰に置き、水やりはやや控えめにします。 冬の管理 霜の当たらない軒下などに移し、水やりはぐっと控えめにします。 ふやし方 花の咲いた株は花後に枯れてしまいますが、株の周りに子株ができますので、春に株分けして増やすことができます。 肥料 多肥にする必要はありません。春と秋に、月に2回程度薄めの液肥を与える程度にします。 病気・害虫 クロツバメシジミの幼虫の食害に注意します。また、過湿にすると根腐れを起こすことがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|