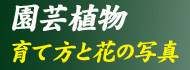|
| |||||||||||||||||||
スイレン |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【スイレンについて】 |
|||||||||||||||||||
|
スイレン(睡蓮)は、ハスと並んで水生植物の代表ですが、ハスの花は水面よりも高い位置で咲くのに対し、スイレンの花は水面に浮いているように咲きます。スイレンは、大きくは、温帯性種と熱帯性種に分けられますが、熱帯性のスイレンは冬を越させることが困難なため、一般には、温帯性の種類が栽培されています。 熱帯性スイレンの中には昼や夜間に咲くものがありますが、温帯性のスイレンは朝咲いて午後には閉じてしまいます。スイレンの名前もこのことに由来していますが、郷土の田宮寅彦先生も「睡蓮の花は昔から知っている。しかし、この花が朝開いて、午後には眠るということは、今年自分の家で作ってみて始めて知った。」と書き残されています。 |
|||||||||||||||||||
【スイレンの概要】 |
|||||||||||||||||||

草丈 草丈という表現はおかしいですが、一般的には水深が株元から10~20㎝ほどが一般的です。 花 大輪から小輪までサイズはいろいろあり、栽培環境に応じて選ぶことができます。花色は白、黄、ピンク、赤などですが、熱帯性スイレンには青や紫の花もあります。 耐寒性・耐暑性
熱帯性スイレンは、冬、室内で水温10度を保てば越冬できます。 ただし、なかなかそういう環境はつくれませんので、一般的には、耐寒性のスイレンを栽培します。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 やや難しい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Nymphaea hybrida 学名の説明 Nymphaea・・・・・ギリシャ・ローマ神話に登場する水の妖精のニンフに由来します。 hybrida・・・・・「雑種の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
|
ここでは、耐寒性種について、種苗会社のカタログに掲載されていたものを紹介します。
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 -私はこう育てる- |
|||||||||||||||||||
|
個々では温帯性のスイレンの育て方について記載しています。 植え付け 球根の植えつけは、3月下旬から4月上旬です。 池などが最適ですが、個人ではそういうわけにいきません。そこで、スイレン鉢などで栽培することになります。8号鉢程度の大きさの鉢に、田土と肥料を入れ、これに植えつけて水中に沈めます。 
置き場所 日当たりが悪いと花付きが悪くなりますので、睡蓮鉢などは日当たりの良いところに置きます。 日常の管理 古い葉や傷んだ葉、咲き終わった花は摘み取るようにします。また、密生しすぎたり、葉が茂りすぎると花つきが悪くなりますので、葉を切り取ってやります。 夏の管理 真夏は水分が蒸発して水位が下がってしまいますので、水位が下がったら水を足してやります。株元から水面まで10~20㎝ほどに保ちます。 冬の管理 温帯スイレンは耐寒性があるため水を張った状態で冬越しが可能ですが、水が少なくなって根茎が水面に出てしまい、寒さで凍ってしまわないようにします。 肥料 植え付け時に、有機質の固形肥料を用土の中に埋め込みます。 病気・害虫 アブラムシが発生することがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|