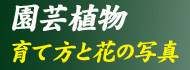|
|
|||||||||||||||||||
サギソウ |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【サギソウについて】 |
|||||||||||||||||||
|
サギソウ(鷺草)は、青森や北海道を除く日本各地、そして台湾や朝鮮に分布するラン科サギソウ属の多年草で、日当たりのよい湿原に自生しています。しかし、最近は乱獲されて、多くの自生地で激減していると言われています。 サギソウは、その名のとおり、シラサギが翼を広げた様に似ていることから人気があり、昔から栽培されてきました。それだけに花の形や葉色の変化などに着目して園芸品種も育成されています。 【栽培メモ】 開花株を購入して育てていたところ、ついつい、冬場の水やりを忘れて、失敗したことがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【サギソウの概要】 |
|||||||||||||||||||

草丈 草丈20~40㎝ほどになります。 花 夏になると花茎が伸びて、 直径3㎝ほどの白花がひとつの花茎に2~3個咲きます。 耐寒性・耐暑性
耐寒性、耐暑性ともあります。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 やや難しい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Pecteilis radiata 学名の説明 Pecteilis・・・・・ギリシャ語の pectein (櫛)が語源です。 radiata・・・・・「放射状の」、「舌状花冠の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 -私はこう育てる- |
|||||||||||||||||||
|
栽培のポイント ※ 植えつけには水ゴケを使うと管理が楽です。 植え付け 球根を植え付ける場合は、芽が出る前の2~3月が適期です。球根の上下がわからないときは、横にして植えても差し支えありません。 使用する鉢は、底の浅い鉢を使った方が見栄えがよいですが、一般的な深さの鉢を使っても栽培する上では全く問題はありません。 植え付けの深さ 球根の上に1~2cmほど用土(水ゴケ)が被る程度にします。 株間 2~3㎝程度の間隔で植え付けます。 鉢植えの用土 植え付けには水ゴケを使うと管理が楽です。水ゴケは半日以上水につけ、絞ってから使います。 そのほか、鹿沼土と水ゴケを等量にしたものなどを使います。 
置き場所 日当たりのよい草地に生える植物ですので、真夏と冬場以外は日当たりのよいところに置きます。 植え替え 植え替えは、毎年2~3月ごろに行います。 初夏に開花株が売られていることが多いですが、これを買ったときは、植え替えは翌年の2~3月春まで待ちます。 日常の管理 元々湿地の植物なので、水切れさせないように注意する必要があります。ただし、真夏を除き、腰水栽培は根腐れの原因になりますのでよくありません。 花が終わったら、早めに取り除いておきます。 夏の管理 真夏は、直射日光を避け、明るい日陰に置くか寒冷紗やすだれなどで遮光します。 水切れには特に注意します。あまり手間をかけられない場合は、真夏だけは受け皿などに浅く水を張って腰水栽培をしても差し支えありません。 冬の管理 葉が枯れたら鉢のまま、冬を越させます。寒さには強いですが、軒下など凍らないところに置きます。 水やりは少なくしますが、月に2~3回程度軽く水やりをして、水ゴケが乾燥しすぎないようにします。 ふやし方 植え替えの時に分球して増やすことができます。 肥料 5~6月と9~10にかけて、月に1回、通常よりも薄めの液肥を与えます。 病気・害虫 ナメクジの食害を受けることがあります。また、ウイルス病が発生すれば、抜き取って処分します。 |
|||||||||||||||||||
|
|