|
| |||||||||||||||||||
オニユリ |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【オニユリについて】 |
|||||||||||||||||||
|
オニユリは元々は中国原産で、栽培していたものが逸出して野生化したものと考えられています。日本にも対馬に変種のオウゴンオニユリが自生しています。 オニユリは葉腋にむかご(珠芽)ができることが特徴のひとつです。また、オニユリの鱗茎は食用にできますが、流通しているのは多くがコオニユリのようです。 【栽培メモ】 午後に日陰になる庭の隅にひとりで生えていてよく咲いていましたが、何らかの事情でなくなってしまいました。最近、オウゴンオニユリを入手して栽培を始めたところです。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【オニユリの概要】 |
|||||||||||||||||||
|
草丈 1〜1.5mほどです。 花 反り返った花弁にオレンジ色の斑点が特徴ですが、花弁が黄色のオウゴンオニユリがあります。 耐寒性・耐暑性
耐寒性、耐暑性があります。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 やさしい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Lilium lancifolium 学名の説明 Lilium・・・・・ギリシャ語の leirion(ユリ)が語源です。 lancifolium・・・・・「披針形の葉の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
対馬に変種のオウゴンオニユリ(L. lancifolium var. flaviflorum)が自生しています。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 −私はこう育てる− |
|||||||||||||||||||
|
植え付け オニユリは大きくなりますので庭植えが一般的なようです。10月中旬〜11月上旬が植えつけの適期です。球根は乾燥を嫌いますので入手したらすぐに植えつけます。 植えつける1週間ほど前に、苦土石灰を1㎡当たり50〜100gほど撒いて耕しておきます。 植えつけに当たっては、腐葉土(又はバーク堆肥)を1㎡当たり10Lほど入れて30〜40cmほど掘り起こします。 植え付けの深さ ユリは、球根から出た茎の土中部分にある根が栄養分を吸収するので、深植えにする必要があります。目安としては球根の3〜4倍ほどにします。 -2.jpg)
植え場所 庭に植える場合は、日当たりと水はけのよいところを好みます。ただし、西日が長く当たるような場所は避けるようにします。 株間 球根と球根の間に2個又は2個半ぐらいが入る程度にします。 植え替え 植えてから数年経つと、何となく元気がなくなりますので10月〜11月上旬に球根を掘り出します。丁寧に分けてから水洗いをして土を落とし、日陰で乾かしたのち、できるだけ早く別の場所に植えつけます。 日常の管理 植え付ければ、後は特段の管理は不要ですが、花が終わったらすぐに摘み取ります。 地上部の葉が半分ほど枯れてきたら、地際で切り戻しをします。 ふやし方 オニユリは種を付けませんが、ムカゴから増やすことができます。秋に、むかごを用土に軽く押し込むように植え付け、覆土はしません。 肥料 庭植えの場合は、植え付け時に、土に被せる土に緩効性の化成肥料を混ぜて植え付け、芽が出る頃に追肥します。 病気・害虫 アブラムシに注意が必要です。そのほか、水はけが悪いと夏の高温時に白絹病が発生することがあります。 |
|||||||||||||||||||
|
|
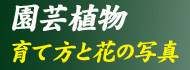

.jpg)