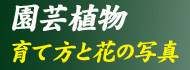|
|
|||||||||||||||||||
フェリシア |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【フェリシアについて】 |
|||||||||||||||||||
|
フェリシアは、南アフリカケープ州原産のキク科ルリヒナギク属の秋まき一年草です。この属には、おなじ南アフリカ原産のブルーデージーと呼ばれる多年草のアメロイデス(Felicia amelloides)がありますが、通常、フェリシアと言えば秋まき一年草のヘテロフィラ(F. heterophylla)を指します。 この花の特徴としては、ブルーの色彩がよく目立つことで、まとまって咲くとなかなか見栄えがします。また、花色のミックスされたタネを播いて育てると、ブルー以外の花が咲きますので、花壇に変化が生まれます。 【栽培メモ】 タネを播いてポットに植え替えるまでは特に難しいことはありませんでしたので、育苗は容易です。 耐寒性がやや弱いので、秋に花壇に定植して冬場は農ポリでトンネルをして育てたところ、部分的に過湿になったため一部の株が枯れましたが、まずまずよい花を見ることができました。 その後、今度は不織布でトンネルをしましたが、最近の温暖化の影響もあってか、特に寒さで傷むことはありませんでした。 |
|||||||||||||||||||
【フェリシアの概要】 |
|||||||||||||||||||

草丈 30cmほどのコンパクトな株になりますので、花壇は勿論、鉢植えやプランターにも向いています。 株元から分枝し、ブッシュ状になります。 花 花径は3㎝で、ブルーの他ピンク、ローズ、パープルなどがあります。 耐寒性・耐暑性
寒さに弱いので、一部の温暖地を除いて、冬は霜よけが必要です。耐暑性はなく、花後に枯れてしまいます。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 ※ タネから育てる場合:比較的やさしい ※ 苗から育てる場合:やさしい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Felicia heterophylla 学名の説明 Felicia・・・・・・ felix(恵まれている、幸運な)が語源とされています。 heterophylla・・・・・「異形葉の」、「多形葉の」 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 −私はこう育てる− |
|||||||||||||||||||
|
栽培のポイント ※ 秋に花壇に定植した場合、不織布でトンネルをするなどの霜除けが必要です。 ※ 鉢植えは、やや乾燥気味に育てます。 タネまき 発芽適温は15〜25度ですので、9月中旬〜10月上旬頃に播きます。通常は箱まきで、覆土は2mm程度にします。播く時期が遅くなると、春までに充実した株にならないので、満足できる花を見ることができなくなる恐れがあります。 
本葉が3〜4枚のころにポリポットに植え替えて育苗します。 植え付け 花壇に植える場合は、植えつけ前に苦土石灰を1㎡あたり100g程度撒いて耕しておきます。 植え付ける際は、腐葉土(又はバーク堆肥)を1㎡当たり10Lほど入れて、庭土を深さ30cmほど耕しておきます。 本葉が5〜7枚ほどになってポリポットの底に根が回ったら定植します。耐寒性がやや弱いので、花壇に植える場合は、温暖地以外は冬はフレーム内に置き、春に定植したほうが安全です。 鉢植えの用土 市販の草花用培養土、あるいは、赤玉土と腐葉土(バーク堆肥)を2対1程度に混ぜたものなどを使います。 株間 20㎝ほどの間隔とします。鉢植えの場合は、5号鉢に1本植えとします。標準のプランターでしたら3〜4株が目安です。 植え場所・置き場所 花壇に植える場合は、日当たりと水はけのよいところに植え付けます。 鉢やプランターに植えた場合も、日当たりのよいところに置いて育てます。 日常の管理 鉢やプランターに植えている場合は、水のやりすぎに注意し、やや乾燥気味に育てます。過湿にすると蒸れてしまいます。 終わった花をそのままにしておくと見苦しくなるので、早めに摘み取ります。 冬の管理 秋に花壇に定植した場合、そのままだと関東以西の温暖地でも冬の寒さで傷んでしまうので、不織布でトンネルをするなどの霜除けが必要です。 鉢植えの場合は、軒下など霜の当たらないところに置きます。 
肥料 花壇に植える場合は、植え込み時に化成肥料を1㎡当たり50gほど入れて庭土とよく混ぜておきます。追肥はほとんど必要ありません。 鉢やプランターに植える場合は、元肥として緩効性の化成肥料を入れ、暖かくなってきたら追肥として月に2回程度液肥を与えます。市販の草花用の培養土を使用するときは、培養土に元肥が入っていますので、元肥は不要です。 病気・害虫 アブラムシがつくことがあります。 |
|||||||||||||||||||