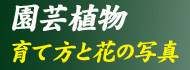ピティロディア |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【ピティロディアについて】 |
|||||||||||||||||||
|
ピティロディアは、オーストラリア原産のシソ科の常緑低木で、20種ほどが知られているようです。このうち、国内で流通しているのは、枝葉の白毛が美しいシルバーリーフが特徴でピンクの花が咲くテルミナリス(P. terminalis)という種類です。 フェアリーピンクという名前で呼ばれることもありますが、これは品種名というよりも流通名のようです。園芸店やホームセンターなどでも、それほど見かけることは少ないですが、日本の気候にはあまり適してないことが要因のようです。 【栽培メモ】 秋にポット苗を購入して、冬は無加温のミニ温室に入れていたところ3月になって咲き始めました。その後、管理が不十分のせいもあって、残念ながら夏が来る頃には枯れてしまいました。夏の高温多湿が苦手なようです。 |
|||||||||||||||||||
【ピティロディア・テルミナリスの概要】 |
|||||||||||||||||||
|
草丈 50㎝~1mほどになります。枝葉の白毛が美しいのが特徴です。 花 ピンクのベル状の花が咲きます。 耐寒性・耐暑性
極端な暑さ、寒さを嫌いますが、冬は霜に当てなければ0度まで耐えるようです。 (強い、比較的強い、やや弱い、弱い、の4区分。判断基準は、こちら) 栽培難易度 ※ 1年だけ育てる場合:比較的やさしい ※ 翌年も育てようとする場合:(温暖地では)かなり難しい (やさしい、比較的やさしい、やや難しい、かなり難しい、の4区分) 学名 Pityrodia terminalis 学名の説明 Pityrodia・・・・・ギリシャ語の pityron(外皮、殻)が語源です。原種のうろこ状の葉に由来します。 terminalis・・・・・「頂生の」 ※ 「頂生」とは、茎や枝の先端に花などをつけることです。 |
|||||||||||||||||||
【主な種類と品種】 |
|||||||||||||||||||
フェアリーピンクという品種が出回っています。 |
|||||||||||||||||||
【 育て方 】 -私はこう育てる- |
|||||||||||||||||||
|
栽培のポイント ※ 夏場は、できるだけ涼しいところに置きます。 植え付け 高温多湿と寒さに弱いので、通常は、鉢植えで育てます。園芸店やホームセンターなどには、春に開花株が出回ることが多いですが、秋にポット苗が出ていることもあります。 購入した株の鉢が小さいようでしたら、花後に大きめの鉢に植え替えます。また、ポット苗の場合は、できるだけ早く、根鉢を崩さないようにして、一回りか二回り大きめの鉢に植え替えます。 
鉢植えの用土 水はけのよい用土に植え付けます。私は、赤玉土、軽石砂、バーク堆肥を5:2:3程度にした用土に植え付けていましたが、夏が来るまでは、まずまずというところでした。 置き場所 秋から春の間は、日当たりのよいところに置きます。 オーストラリア原産の植物は、梅雨と夏の高温多湿を嫌うものが多いですが、ピティロディアも同様ですので、梅雨時や長雨になりそうなときは、雨の当たらないところに移します。 植え替え 花後に植え替えをします。 日常の管理 水はけのよい用土に植えて、過湿にならないように管理します。 花が終わったら切り戻しをしておくと、側枝が伸びて花が咲きます。また、秋の終わりに全体を切りもどしておきます。 夏の管理 高温多湿を嫌いますので、初夏になったら半日陰に、真夏は明るい日陰の風通しのよい涼しいところに置いて管理します。 冬の管理 耐寒性は強くないので、冬は霜の当たらない軒下に置きます。乾燥気味にして水やりは少なくしますが、鉢土がよく乾いたら晴れた日の午前中に水やりをします。 肥料 春と秋に緩効性の固形肥料を置肥します。 病気・害虫 特にはないようです。 |
|||||||||||||||||||